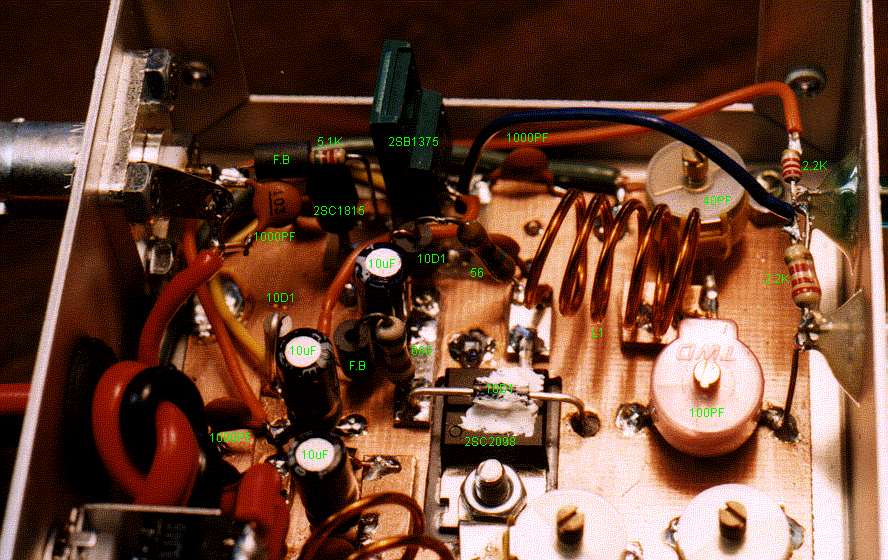 入力部のクローズアップ
入力部のクローズアップ
 前述のように、FL-6020がでかくて重いのは、外見から見る限りは放熱板が原因のようです。これが無くせれば相当な軽量化ができそうです。さて、それは可能か? 答えはYES。ただし条件付きですけど。
前述のように、FL-6020がでかくて重いのは、外見から見る限りは放熱板が原因のようです。これが無くせれば相当な軽量化ができそうです。さて、それは可能か? 答えはYES。ただし条件付きですけど。上記2つの理由で、今回は放熱板は付けずにケースを放熱板として利用します。その他、小型化のためにフィルタにはトロイダルコアを使用し、接近してもコイルの相互結合が最小限になるようにしました。コネクタの重さもバカにできないのでBNCにしました。
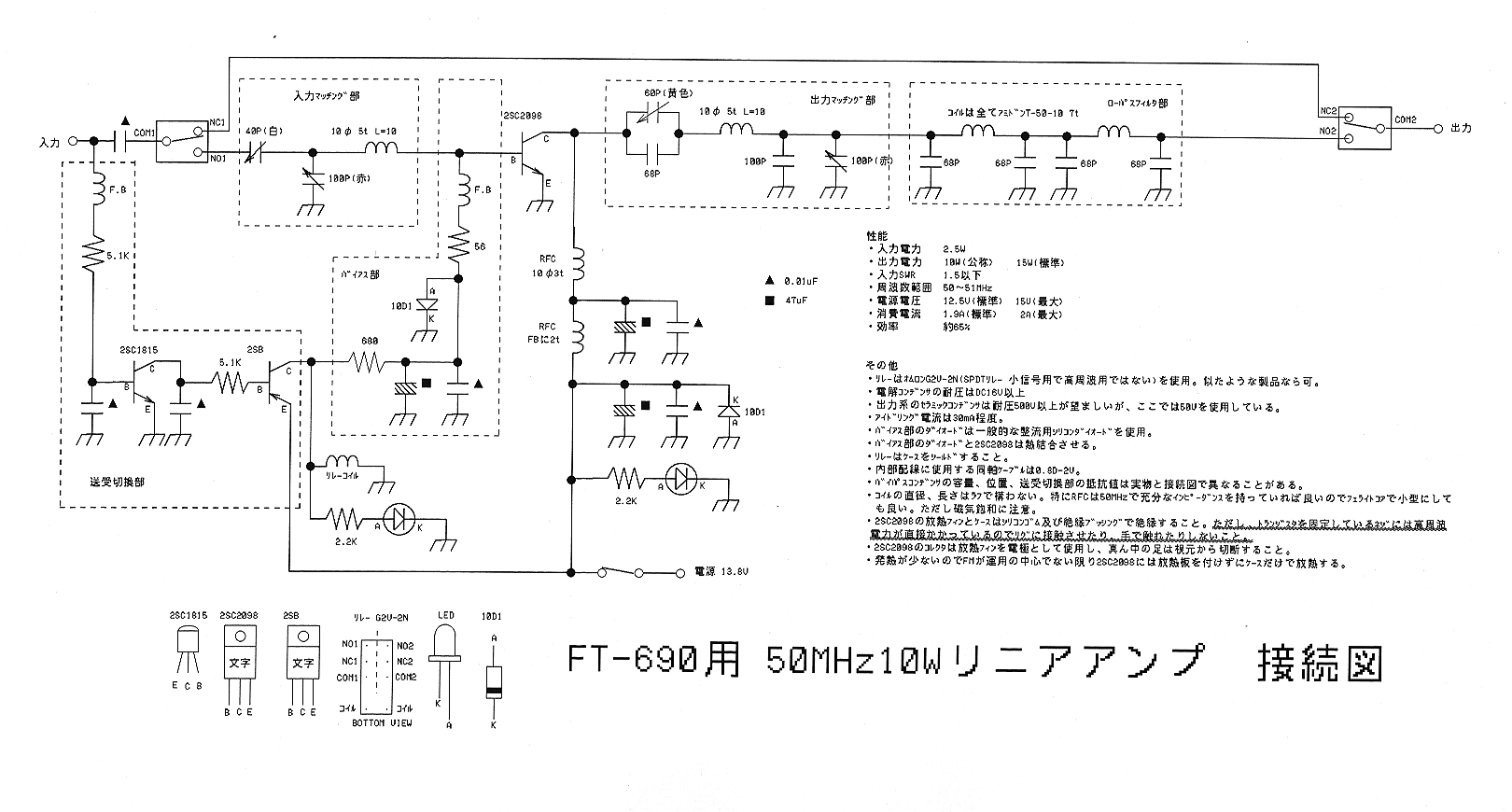 リニアアンプの回路自体はごく有り触れたもので、目立った特徴はありません。各種雑誌の回路を参考にしました。ただし、今回は出力の目標を10W以上にしましたので、若干マッチング回路の定数が変わっています。その影響で帯域幅が狭くなってSWRが1.5以下の周波数帯域は約1MHzです。むろん、今回はSSB/CWしかターゲットにしていないので問題ありません。
リニアアンプの回路自体はごく有り触れたもので、目立った特徴はありません。各種雑誌の回路を参考にしました。ただし、今回は出力の目標を10W以上にしましたので、若干マッチング回路の定数が変わっています。その影響で帯域幅が狭くなってSWRが1.5以下の周波数帯域は約1MHzです。むろん、今回はSSB/CWしかターゲットにしていないので問題ありません。
出力には高調波によるTVI防止のために、定K型ローパスフィルタを2段挿入しています。山では周囲に人家はないので問題ありませんが、住宅地で使う場合には外付けでフィルタを追加するのが無難です。
送受信切換回路が通常のアンプと異なっています。一般に、リニアアンプは親機がどんなリグでも接続できるようにキャリアコントロール方式を採用していますが、これですと電波が出てから切り替わるまでに時間がかかり、会話の頭が途切れます。特にCWですと短点が消失することもあります。そこで、今回は親機を改造して、送信時には同軸ケーブルの芯線にDC電圧を乗せるようにします。アンプ側ではDCとRF信号を分離し、DC電圧でトランジスタスイッチを駆動します。トランジスタスイッチは2石で構成し、最終的には中電力PNPトランジスタで電源をON/OFFします。
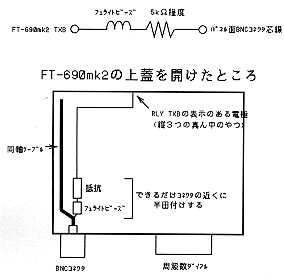 本体はなるべくでしたら触りたくありませんが、一度この改造をしておくと他のリニアアンプを接続したり、トランスバータやプリアンプなど、付加機器の送受信切換に広く応用できて便利です。それほど難しい改造ではないので、保証期間が切れていたり、自作をする人なら改造をお奨めします。ただし、改造による故障は筆者は責任を持ちません。各自の責任で行って下さい。過去に2台の改造を行いましたが支障はありませんでした。勿論、FT-690mk2の接続図を調査し、回路的に支障がないからこそ改造したのですが。
本体はなるべくでしたら触りたくありませんが、一度この改造をしておくと他のリニアアンプを接続したり、トランスバータやプリアンプなど、付加機器の送受信切換に広く応用できて便利です。それほど難しい改造ではないので、保証期間が切れていたり、自作をする人なら改造をお奨めします。ただし、改造による故障は筆者は責任を持ちません。各自の責任で行って下さい。過去に2台の改造を行いましたが支障はありませんでした。勿論、FT-690mk2の接続図を調査し、回路的に支障がないからこそ改造したのですが。
FT−690用10Wリニアアンプ 部品表 +−−−−−−−−−−−−−+−−−−+−−−−−−−−+ | 品 名 | 個数 | 購入場所 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−+−−−−−−−−+ |2C2098 | 1 | 小沢電気 | |10D1 | 2 | 秋月電子 | |2SC1815 | 1 | 秋月電子 | |2SB1375 | 1 | 千石電商 | |赤色LED | 1 | 千石電商 | |緑色LED | 1 | 千石電商 | |100P フィルムトリマ | 2 | 千石電商 | |68P フィルムトリマ | 2 | 斉藤電気 | |68P セラミック | 5 | 千石電商 | |100P セラミック | 1 | 千石電商 | |0.01uF セラミック | 6 | 秋月電子 | |10uF 16V 電解 | 3 | 秋月電子 | |56Ω 1/4W | 1 | 千石電商 | |680Ω 1/4W | 1 | 千石電商 | |2.2KΩ 1/4W | 2 | 千石電商 | |5.1KΩ 1/4W | 2 | 千石電商 | |G2V−2 DC12V | 1 |忘却(^_^;)| |電源スイッチ | 1 | 千石電商 | |0.8D−2V | 1 | 小柳出電線 | |ビニール導線 | 1 | 在庫品 | |T−50−10 | 2 | 斉藤電気 | |シリコンゴム | 1 | 千石電商 | |絶縁ブッシング | 1 | 千石電商 | |ケース(YM−100) | 1 | 千石電商 | |M3×5 ネジ | 13 | 適当 | |卵ラグ | 4 | シオヤ電気 | |ゴムブッシング | 1 | 千石電商 | |BNC−R | 2 | 千石電商 | |フェライトビーズ | 4 | 千石電商 | |φ1mmポリウレタン | 1 | 小柳出電線 | |生基板 | 1 | 秋月電子 | +−−−−−−−−−−−−−+−−−−+−−−−−−−−+

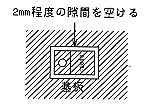 次に基板の加工です。まず、ケースに入りきる大きさに基板を切断します。ギリギリの大きさだと作業時の誤差でケースに入らないこともありますので、少し小さめにします。次に基板の4隅にケースに固定するための穴を開けます。そして基板の中心付近に四角いトランジスタの取り付け穴を開けます。これも現物あわせで行います。穴の大きさはトランジスタよりも2mm程度大きく開けて、基板の銅箔とトランジスタの放熱フィンが接触しないように注意します。フィンはトランジスタのコレクタとつながっているため、基板とフィンが接触すると電源がショートして電源ケーブルが燃えてしまいます。
次に基板の加工です。まず、ケースに入りきる大きさに基板を切断します。ギリギリの大きさだと作業時の誤差でケースに入らないこともありますので、少し小さめにします。次に基板の4隅にケースに固定するための穴を開けます。そして基板の中心付近に四角いトランジスタの取り付け穴を開けます。これも現物あわせで行います。穴の大きさはトランジスタよりも2mm程度大きく開けて、基板の銅箔とトランジスタの放熱フィンが接触しないように注意します。フィンはトランジスタのコレクタとつながっているため、基板とフィンが接触すると電源がショートして電源ケーブルが燃えてしまいます。
+----+----+----+----+ | | L1 | L2 | L3 | +----+----+----+----+ |内径|10mm|10mm|10mm| +----+----+----+----+ |巻数|5回 | 5回| 3回| +----+----+----+----+ |長さ|10mm|10mm|10mm| +----+----+----+----+
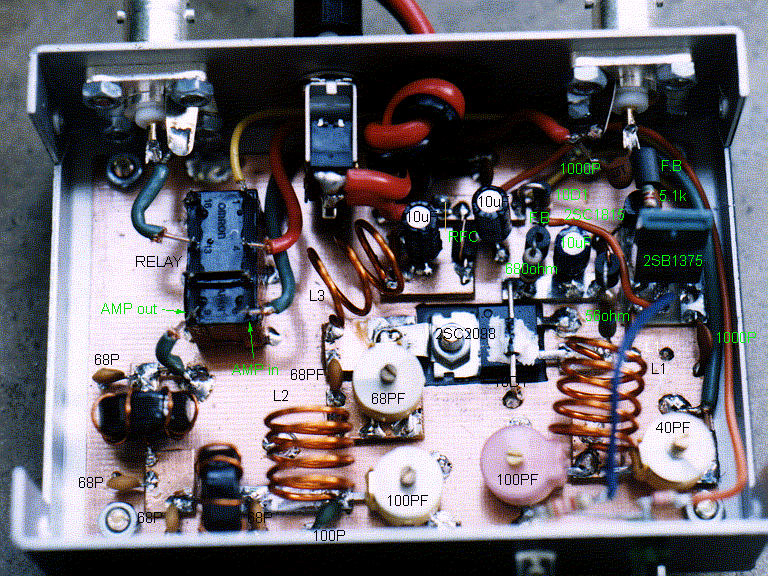 全体像
全体像
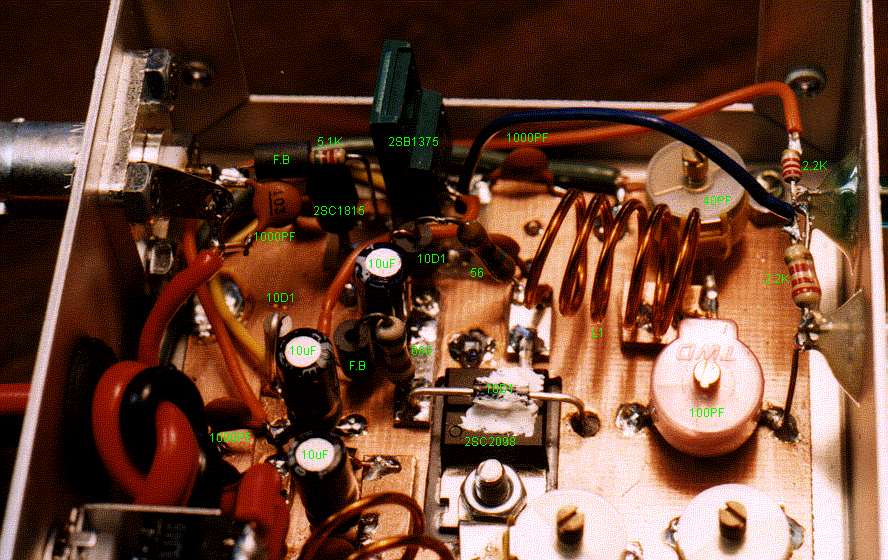 入力部のクローズアップ
入力部のクローズアップ
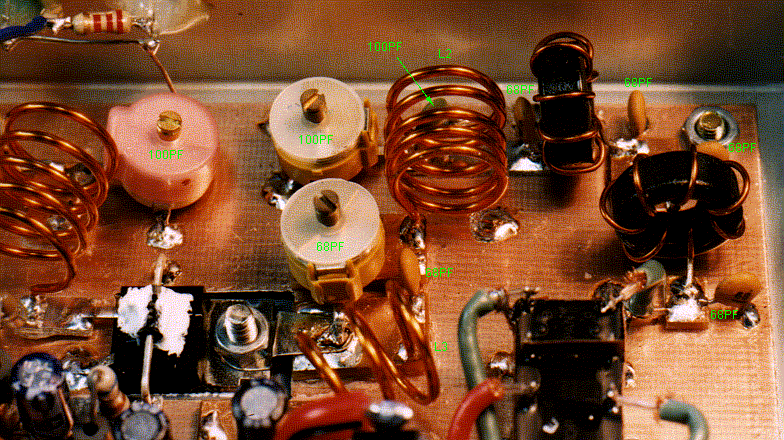 出力部のクローズアップ
出力部のクローズアップ
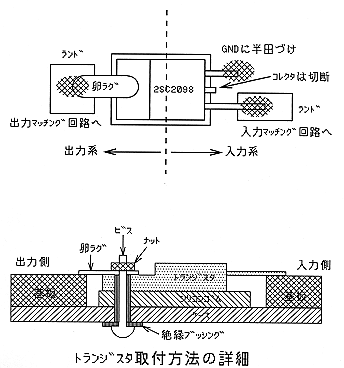 さて、いよいよ基板の半田付けです。 部品配置の写真を参考にしながら、現物の部品に合わせながらランドを貼り付けて半田付けしていきます。最初に2SC2098を半田付けし、ここを基準に回りの部品配置を決めます。トランジスタの取り付けは少し変わった方法を採用しました。入出力を分離して安定動作を確保する狙いのためです。トランジスタの3本の足の真ん中がコレクタですが、実は放熱フィンはコレクタに接続されています。ベースとコレクタが隣り合っていますので、このままだと入出力のマッチング回路が接近し、磁界やストレーキャパシタを介して結合し、発振する恐れがあります。そこで、真ん中のコレクタは根元で切断し、放熱フィンから卵ラグでコレクタと接続します。この方法ですとトランジスタの頭とお尻に入出力が物理的に分離されて発振しにくくなります。放熱フィンはコレクタに接続されているので、ケース(GND)と絶縁する必要があります。ケースとの間にシリコンゴム板をはさみ、取り付けネジは絶縁ブッシングを通します。ただし、ケースへの取り付けはまだ行いません。この方法ですとネジには高周波信号が直接かかってしまい、運用中に触れたり、リグと接触させると危険です。本当は図とは逆に絶縁ブッシングをトランジスタ側に取り付けるといいのですが、それには卵ラグの穴を4mmに広げる必要があります。ところが、卵ラグは薄い金属板で強度が弱く、ドリルで穴を広げようとしても変形してしまい加工できません。ヤスリで根気よく削ればいいのですが、手間がかかるので今回は上記のような固定方法で妥協しています。新たに製作されるみなさんは、反対にした方が無難です。
さて、いよいよ基板の半田付けです。 部品配置の写真を参考にしながら、現物の部品に合わせながらランドを貼り付けて半田付けしていきます。最初に2SC2098を半田付けし、ここを基準に回りの部品配置を決めます。トランジスタの取り付けは少し変わった方法を採用しました。入出力を分離して安定動作を確保する狙いのためです。トランジスタの3本の足の真ん中がコレクタですが、実は放熱フィンはコレクタに接続されています。ベースとコレクタが隣り合っていますので、このままだと入出力のマッチング回路が接近し、磁界やストレーキャパシタを介して結合し、発振する恐れがあります。そこで、真ん中のコレクタは根元で切断し、放熱フィンから卵ラグでコレクタと接続します。この方法ですとトランジスタの頭とお尻に入出力が物理的に分離されて発振しにくくなります。放熱フィンはコレクタに接続されているので、ケース(GND)と絶縁する必要があります。ケースとの間にシリコンゴム板をはさみ、取り付けネジは絶縁ブッシングを通します。ただし、ケースへの取り付けはまだ行いません。この方法ですとネジには高周波信号が直接かかってしまい、運用中に触れたり、リグと接触させると危険です。本当は図とは逆に絶縁ブッシングをトランジスタ側に取り付けるといいのですが、それには卵ラグの穴を4mmに広げる必要があります。ところが、卵ラグは薄い金属板で強度が弱く、ドリルで穴を広げようとしても変形してしまい加工できません。ヤスリで根気よく削ればいいのですが、手間がかかるので今回は上記のような固定方法で妥協しています。新たに製作されるみなさんは、反対にした方が無難です。
この部分の組立には、仮に基板をケースに固定して行います。そうでないとトランジスタの穴と、トランジスタを取り付けるためにケースに開けた穴の位置がずれて入らない・・・となる恐れがあります。トランジスタを固定したらコレクタ(放熱フィン)、ベースの部分にランドを張り付け、半田付けします。エミッタの半田付けもお忘れ無く。ここまでやったらケースから基板を外して作業します。位置の精度が必要なのは2SC2098の穴だけです。
バイアス部の10D1は、2SC2098の上面に接触させて、シリコングリスを塗って熱的に結合させます。抵抗、コンデンサ等の部品の足はできるだけ短くカットして、最短距離で半田付けして下さい。安定動作の秘訣です。部品を取って再利用しよう、なんて考えて足を長めにしてはいけません。動作不良のトラブルに泣かされます。イモ半田にも注意。また、時々ケースに入れてみて、部品がコネクタやスイッチに当たらないか確認して下さい。リレー周囲の配線はケースに組み込む段階で行いますのでまだ行わないで下さい。図に示した範囲を組み立てます。
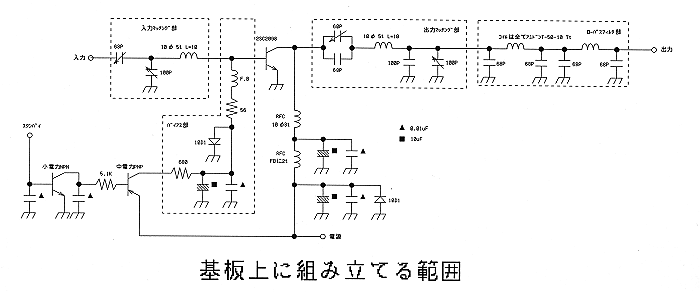
・終端型電力計(MAX15W以上) 無ければ通過型電力計とダミーロードを組み合わせて使用。
・SWRメータ
・テスタ(2A 程度の電流計、15V程度の電圧計)
・電源装置 13.5V 3A以上 できれば電流制限機能付きが望ましい
・ワニ口電線
・接続用同軸ケーブル
・トリマ調整用の絶縁物でできた調整棒
まず、入力と出力にコネクタ付きのケーブルを半田付けします。そうしないとリグやSRWメータ等と接続できません。1.5D-2Vで作っておくと引き回しがしやすくて重宝します。リグやSWRメータとの接続ケーブルも1.5D-2Vが適当です。20cmくらいの長さの物を2、3本作っておくと何かと便利です。電源ケーブルも付けます。電源ケーブルの+,-間の抵抗値をテスタで測定し、数kΩ以上ならOKです。ゼロだったり、非常に低い値の時にはどこかで電源系統とGNDが接触したり、パスコン関係が不良と思われます。チェックして下さい。試験中はトランジスタが発熱するので、ケースを裏返しにして、ケースの外側に仮に基板を固定して、ケースを放熱板として利用します。前記のようにトランジスタの放熱フィンとケースはシリコンゴム、絶縁ブッシングで絶縁して下さい。勿論、普通の放熱板やアルミ板に取り付けて試験しても構いません。トランジスタの放熱フィンとケースが導通していないか確認して下さい。
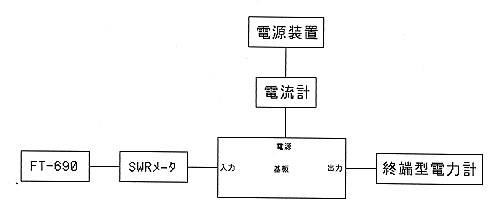 図のように接続し、690をFMモードにして、自分のよく使う周波数に合わせます。2.5Wで送信し、SWR計の表示は無視してパワーメータだけ見ながら、入力マッチング回路の2つのトリマ、続いて出力マッチング回路の2つのトリマを、出力が最大になるように調整します。もし、トリマの羽がいっぱいに入ったり、逆に抜けきったところで最大パワーになる場合は、コイルを延ばしたり縮めたりして、もう一度調整します。どうしてもうまく行かないときにはトリマと並列に入っている固定コンデンサの値を増減したり、コイルの巻き数を1回増減させて再調整します。ほとんどの場合はコイルの巻き数を変更する必要はないはずです。うまく調整できれば10W近く出ます。なお、調整中はまだアンプのSWRが高い状態で、親機に悪影響を与えますので、できるだけ短時間の送信で調整して下さい。
図のように接続し、690をFMモードにして、自分のよく使う周波数に合わせます。2.5Wで送信し、SWR計の表示は無視してパワーメータだけ見ながら、入力マッチング回路の2つのトリマ、続いて出力マッチング回路の2つのトリマを、出力が最大になるように調整します。もし、トリマの羽がいっぱいに入ったり、逆に抜けきったところで最大パワーになる場合は、コイルを延ばしたり縮めたりして、もう一度調整します。どうしてもうまく行かないときにはトリマと並列に入っている固定コンデンサの値を増減したり、コイルの巻き数を1回増減させて再調整します。ほとんどの場合はコイルの巻き数を変更する必要はないはずです。うまく調整できれば10W近く出ます。なお、調整中はまだアンプのSWRが高い状態で、親機に悪影響を与えますので、できるだけ短時間の送信で調整して下さい。
次にSWRメータを見ながらSWRが最低になるように入力の2つのトリマを調整します。若干パワーが落ちますが、仕方ありません。SWRは悪くても必ず1.1以下にできます。
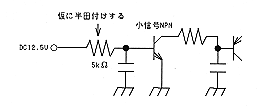 以上の調整は、まだバイアス電流を流していませんのでブースターとしての動作ですが、いよいよリニアアンプとしての調整に入ります。とは言っても今までの調整でほとんど終わっています。出力側のRFCを外して電流計モードにしたテスタを接続します。2SC1815のベースに5KΩの抵抗を仮に半田付けし、抵抗を電源と接続します。するとテスタに電流が流れます。この電流値が20〜40mA程度であることを確認します。えらくかけ離れている場合はバイアス部に誤配線がありますのでチェックして下さい。正常でしたらRFCを元に戻します。
以上の調整は、まだバイアス電流を流していませんのでブースターとしての動作ですが、いよいよリニアアンプとしての調整に入ります。とは言っても今までの調整でほとんど終わっています。出力側のRFCを外して電流計モードにしたテスタを接続します。2SC1815のベースに5KΩの抵抗を仮に半田付けし、抵抗を電源と接続します。するとテスタに電流が流れます。この電流値が20〜40mA程度であることを確認します。えらくかけ離れている場合はバイアス部に誤配線がありますのでチェックして下さい。正常でしたらRFCを元に戻します。
電源を再投入してパワーメータの振れを見ます。このとき、リグは受信状態のままにして下さい。当然ながら、入力がないので出力も無いはずですが、もしパワーメータの針が振れていたらアンプが発振している証拠です。きっと電流計の振れも大きいでしょう。このままでは使えないので、パスコンのセラミックコンデンサを追加したり、入力側のRFCと並列に1kΩ程度の抵抗を入れたり、トランジスタ上に入出力を分離するようにシールド板を立ててみます。でも、図のように部品配置を真似すればたぶん発振はしないでしょう。オリジナルの部品配置は、発振しにくいように考慮して決定していますし、4台製作して4台とも発振しませんでした。もともと、CB用のトランジスタを高い周波数で使っているので利得が低下して発振しにくくなっています。
発振しないことが確認できたらFT-690を送信状態にして、パワー最大、SWR最低になるようにトリマを再調整します。でも、今までの調整でベストポイント近くにあるはずで、ほとんどトリマを回す必要はないでしょう。パワーはさっきよりも増えて10W以上出るはずです。
ここまでくれば、全体の90%は完成したようなものです。基板単体は立派なリニアアンプとして動作しました。
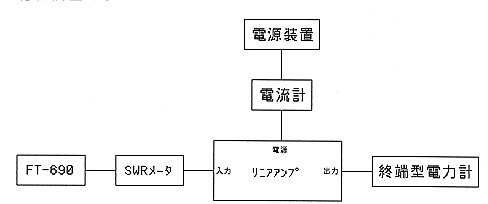 最初は上図からSWRメータを抜いてセットアップします。モードをCWにしてPTTを押し、リレーが切り替わることを確認します。もし切り替わらない場合は送受信切換部をチェックしてください。次に入力側にSWR計を入れます。この状態ですとSWR計のタイプによりますが、PTTを押しても送信状態にならない時があります。これはものによってはSWRメータ内部がDC的に絶縁もしくはショートされているためです。このときは、2SC1815のコレクタをワニ口クリップ付きのケーブルでGNDに接触させて、強制的にリニアアンプを送信状態にして下さい。リグから送信してSWRが下がっていることを確認します。もし上がっていたらトリマを再調整します。また、出力が最大になるようにも調整して下さい。OKなら蓋を閉め、SWR、パワーを確認します。若干出力の増減はありますがさっきとほぼ同じなら完成です。パワーの低下が気になる人は、蓋を閉めた状態でパワーが最大になるように再調整して下さい。どうです? 15Wくらい出たでしょう。10W以上出ていれば合格です。電流は出力電力によりますが、15W程度なら1.8〜1.9A程度に収まっていることと思います。動作が確認できたらLEDが引っ込まないようにケース内部でエポキシで固めてしまいます。これでLEDの頭が押されても大丈夫、エポキシの接着力は相当です。
最初は上図からSWRメータを抜いてセットアップします。モードをCWにしてPTTを押し、リレーが切り替わることを確認します。もし切り替わらない場合は送受信切換部をチェックしてください。次に入力側にSWR計を入れます。この状態ですとSWR計のタイプによりますが、PTTを押しても送信状態にならない時があります。これはものによってはSWRメータ内部がDC的に絶縁もしくはショートされているためです。このときは、2SC1815のコレクタをワニ口クリップ付きのケーブルでGNDに接触させて、強制的にリニアアンプを送信状態にして下さい。リグから送信してSWRが下がっていることを確認します。もし上がっていたらトリマを再調整します。また、出力が最大になるようにも調整して下さい。OKなら蓋を閉め、SWR、パワーを確認します。若干出力の増減はありますがさっきとほぼ同じなら完成です。パワーの低下が気になる人は、蓋を閉めた状態でパワーが最大になるように再調整して下さい。どうです? 15Wくらい出たでしょう。10W以上出ていれば合格です。電流は出力電力によりますが、15W程度なら1.8〜1.9A程度に収まっていることと思います。動作が確認できたらLEDが引っ込まないようにケース内部でエポキシで固めてしまいます。これでLEDの頭が押されても大丈夫、エポキシの接着力は相当です。
(1) アンプの放熱板は、山岳移動でのSSB運用に必要な最小限の大きさです。気温の
高い場所やFMで長時間運用するときには過熱に注意して下さい。
(2) 誤って10Wを入れるとトランジスタを破壊する恐れがあります。ドライブ電力には十分
注意して下さい。
(3) 内部は電源逆接続保護ダイオードにより保護されていますが、逆接続するとダイオード
が導通して電源ケーブルには非常に大きな電流が流れ、ケーブルが燃える恐れがあります。
必ず外部に2〜3Aのヒューズを入れて下さい。
(4) ケース上面に絶縁ブッシングを介して取り付けられているネジは、パワートランジスタのコレクタに
接続されていて高周波電力がかかっています。運用中は手で触れたり、リグに
接触させないように注意して下さい。絶縁テープ等で覆うのも有効な手段です。
ただし、放熱効果が落ちますのでネジ以外の部分を覆わないで下さい。
(5) 一応ローパスフィルタが入っていますが、人家のない山岳運用用に作っています。
スプリアス抑圧が充分であるといえるか不明ですので、固定で使用する場合は
ローパスフィルタを外付けすることを推奨します。もしくはトロイダルコアを使用したフィルタを
内部に追加して下さい。
(6) 小型化/低コスト化のために高周波系のコンデンサの耐圧にはあまり余裕がありません。
アンテナのSWRが高いと定在波がコンデンサの耐圧を越えて故障の原因となります。
極力、アンテナのSWRは低く保って下さい。